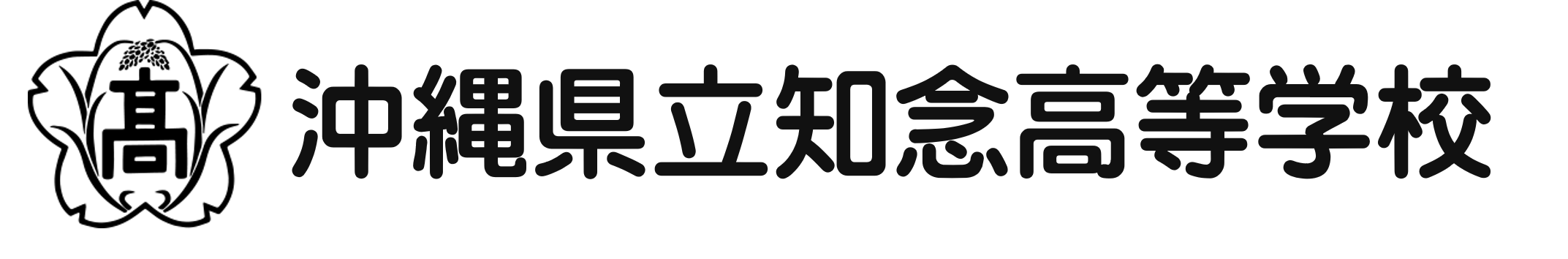学校沿革の概要
本校は、紺碧の空の下、上の森を背に、雄大な青い海原の中城湾を身近に眺望できるところに位置し、今年79年目を迎える伝統校です。 本校は、昭和20年(1945年)11月16日、知念市志喜屋区(20日間)に創立し、開校式が挙行されました。 その後、戦後の混乱の中、同市百名区(4か月間)、玉城村親慶原区(5年11か月間)へと所在地を移転、昭和27年(1952年)2月17日、与那原町に落ち着き、現在にいたっています。 当初、男子部・女子部と分離していましたが、昭和22年(1947年)に男女共学となり、昭和23年(1948年)に旧制高校4年制から新制高校6・3・3制へ移行、 昭和31年(1956年)に夜間定時制を設置[昭和49年(1974年)廃止]、昭和47年(1972年)に琉球政府から沖縄県立へと幾多の変遷を経てまいりました。 87名でスタートした生徒も令和4年度末現在、卒業生は29,340名に達し、建学の精神の下優秀な人材を輩出し、県内外の各界角層で活躍しています。
教育目標
意欲に燃えた、節度ある、心身ともに健全で、創造性豊かな、逞しい人間の育成を目指す
校章
沖縄で初めて稲が植えられたのは、南城市玉城字百名の受水走水(ウキンジュハインジュ)といわれ、本校はその地の高台に建てられました。 実るほど垂れ下がる稲 穂は謙虚な態度を意味し、周りを囲む桜花は、若さと情熱と純真な心を意味し、枯渇することのない若々しい無限の創造精神を象徴しています。 全校生徒から募集し、仲西ゆき子氏(2期生)のデザインで1946年 6月11日に制定されました。 現在の校章は、安次富長昭氏(4期生)により1995年10月にリ・デザインされたものです。
校訓
和衷協同(わちゅうきょうどう)
紀元前に書かれた中国の古典『書経』に由来し、「心を同じく して、共に協力し活動する。」という意味です。